∟SEO協会認定試験とは:時代によって変化してきたSEO技術を体系的に理解していることを示す資格検定試験です。
Google アナリティクス認定資格∟Google アナリティクス認定資格とは:SEO対策には欠かせないデータ解析ツール「Googleアナリティクス」の習熟度をGoogleが公式に認定する資格です。

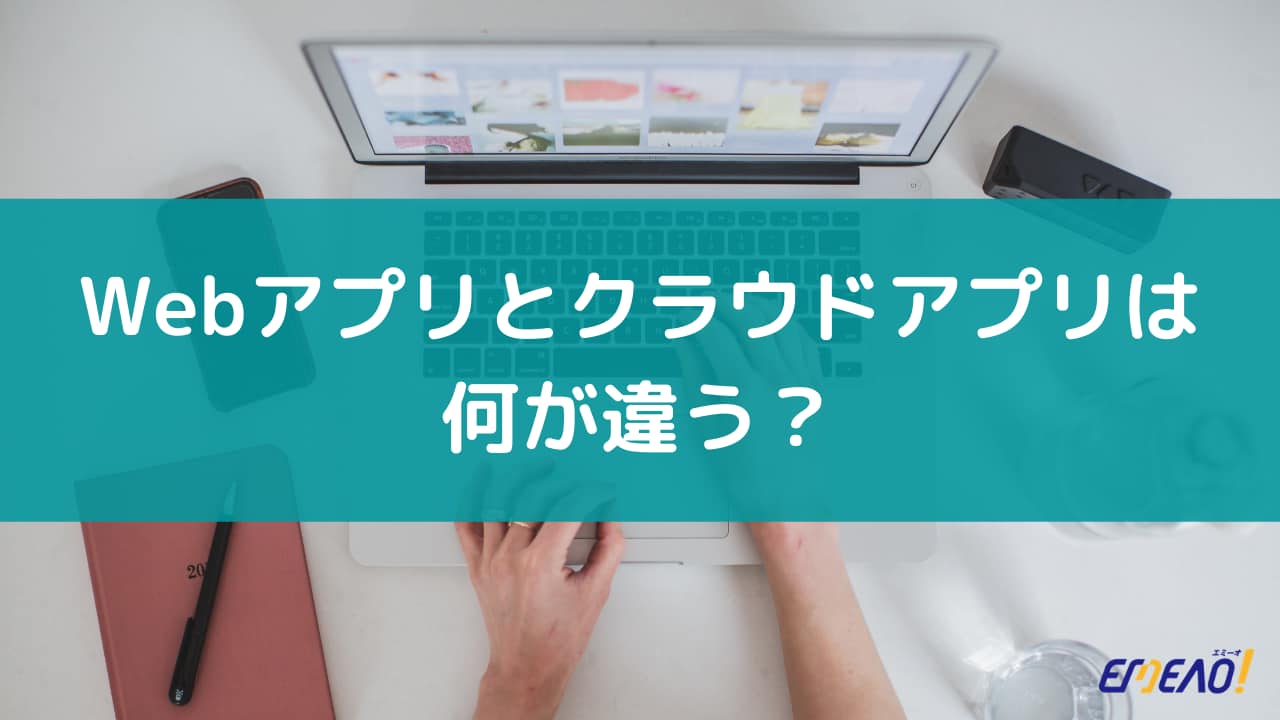
公開日:2020.01.24 最終更新日:2023.11.17
近年導入が進んでいる「クラウドアプリ」について、従来のWebアプリとの違いやメリットについて気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、アプリ開発におけるWebアプリとクラウドアプリの違いについて解説します。
アプリ開発の外注をご検討されている事業者様は、ぜひ最後までご覧ください。
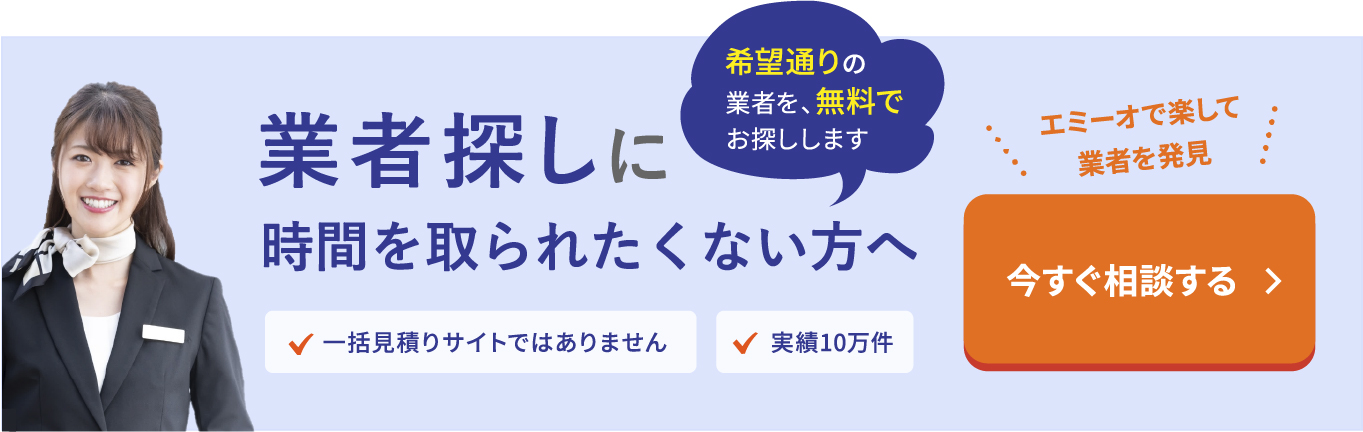

Webアプリとクラウドアプリの大きな違いは、次の3点です。
Webアプリとクラウドアプリの違い
Webアプリとは、インターネット環境においてWeb上で操作可能なアプリであり、Webサービスと呼ばれることもあります。
具体的なWebアプリの例として「Google」「Yahoo!」といった検索エンジンや「Amazon」「楽天市場」のような通販サイト、そのほか「Facebook」「Twitter」といったSNSも挙げられます。
Webアプリのデータはサーバー上で管理され、ユーザーはインターネットへ接続することでブラウザを経由しアプリの動作に必要なデータを取得します。
つまりサーバーから送られてきたデータによってアプリを操作するという点が、Webアプリの特徴といえます。
Webアプリはブラウザを通じ動作可能であるため、PCやスマートフォンといった端末にインストールする必要はありません。
ただしブラウザを経由しインターネットへ接続する必要があるので、オフライン環境ではアプリは動作しません。
オフライン環境ではそもそもアプリを使用できない点に注意が必要です。
クラウドアプリはWebアプリの欠点を改善した点においてWebアプリよりも利便性の高いアプリの形態です。
インターネット環境を通じサービスを利用する仕組みはWebアプリと同じですが「クラウド」という仮想サーバー上にシステムを接続し利用する仕組みになっている点が、Webアプリと大きく異なるポイントです。
Webアプリのようにブラウザからアクセスし利用することも可能ですが、PCやスマートフォンといった端末に専用アプリをインストールすればインターネット環境が無くても利用することが可能です。
具体的には「Evernote」「Dropbox」「zoom」などのアプリがクラウドアプリにあたります。
これらアプリケーションは従来のWebアプリ同様にブラウザ上で操作可能である一方、端末に専用アプリをインストールし利用できるアプリも最近では多く開発されています。
クラウドアプリはWebアプリのように直接サーバーにアクセスするのではなく、複数のサーバー群から構成される「クラウド」という仮想サーバーにアクセスします。
データを複数サーバーに分散させて管理できるため、アプリ側でインターネット接続が切断されたりアプリ内で不具合が起こったりした場合でも稼働し続けることが可能です。
専用アプリを端末にダウンロードしておくことでオフライン環境でも一部機能が利用可能である点において、Webアプリとは仕組みが大きく異なります。
オフライン状態でクラウドアプリを利用した場合、その後オンライン環境に再度接続した際に最新情報(アプリを使用して作成したドキュメントやアップロード済みの画像など)がクラウド上にアップロードされ、アプリに情報が共有されます。
今までのシステム構築は、オンプレミスの利用が主流でした。オンプレミスとは、システムの稼働やインフラストラクチャーを構築するのに必要なサーバーやソフトウェアなどを自社内で管理して運用することを指します。オンプレミスのメリットは、以下の通りです。
オンプレミスのメリット
オンプレミスのデメリットは、以下の通りです。
オンプレミスのデメリット
しかし、最近では徐々にクラウドを利用する機会が増えてきました。クラウドを利用していくにつれて、業務のシステムをまるごとオンプレミスからパブリッククラウドへ変える企業も増えてきました。
クラウドとは、ハードウェアやソフトウェアを持たなくても、インターネットを使ってサービスや機能を利用する分だけ利用するということです。クラウドを使うとインフラストラクチャーを整える必要がなくなります。そのため、その分コストが減らせるというメリットがあるのです。
クラウドは、オンプレミスと同じような役割を果たします。そのため、同一のものとみなされたり、比べられたりなどします。しかし、クラウドとオンプレミスは異なるものです。先述した通り、オンプレミスはシステムの稼働やインフラストラクチャーを構築するのに必要なサーバーやソフトウェアなどを自社内で管理して運用します。一方でクラウドは、サービスや機能などをインターネットを使って外部で使用します。「内」と「外」という明確な違いがあるのです。
また、クラウドは大きく分けて2つに分類されます。プライベートクラウドとパブリッククラウドです。
プライベートクラウドとパブリッククラウドとは
また、SaaS系のビジネスが増えたことによって、クラウドファーストの波が素早く流れ始めました。
SaaSとは、「Software as a Service」の略称で、インターネットを経由することで、サービスを提供している事業主側のソフトウェアを、ユーザーが利用できるようになるシステムのことを指します。SaaSは、インターネットに接続していれば、どのような場所でもサービスが扱えます。また、同じアカウントを使っていれば、どのようなデバイスでも問題なくサービスが使えるのです。ネット社会の現代には、必要不可欠のシステムとなっています。また、1つのプロジェクトに複数人で同時にコメントや編集、修正ができたり、それを別の人に共有したりすることもできます。
SaaSのメリットは、以下の通りです。
SaaSのメリット
SaaSのデメリットは、以下の通りです。
SaaSのデメリット
SaaS系のビジネスには必要不可欠なサーバーの運用を会社の外にあるデータセンターに任せることにして、自社ではサービスの開発や普及に集中するといったビジネススタイルの企業が増えています。素早くコストが低いクラウドアプリケーションの構築が、SaaS系のビジネス事業において重要になります。そのため、短い期間でコストをできる限りかけずに開発ができる上に、異なるクラウド間やオンプレミスでも稼働が可能なクラウドアプリケーション開発に注目するSaaS系のビジネス事業者が増えました。
Webアプリケーションのメリットとデメリットをそれぞれ紹介していきます。Webアプリケーションのメリットとデメリットをそれぞれ把握して、ぜひ今後の自分の開発したいアプリケーションの参考にして下さい。
まずは、Webアプリケーションのデメリットから紹介します。Webアプリケーションのデメリットとしては、以下の4つが挙げられます。
Webアプリケーションのデメリット
とくに、Webアプリケーションのデメリット①の「iPhoneやAndroidなどの端末に付いているカメラやマイクなどの機能が使えない」という点は、大きなデメリットといえるでしょう。例えば、iPhoneやAndroidなどのカメラ機能、プッシュ通知機能、GPS機能などが全く使えなくなります。端末が独自で持っている機能が使えないと、アプリケーションの内容が良くてももったいない気がするという方も多いのではないでしょうか。このようなパソコンやスマホなどの端末が持っている独自の機能のことを「ネイティブ機能」といいます。この「ネイティブ機能」を生かしたアプリケーションを開発したい場合には、Webアプリケーションよりも、ネイティブアプリケーションの開発の方が向いているでしょう。
次に、Webアプリケーションのメリットについて紹介します。Webアプリケーションのメリットは、以下の4つです。
Webアプリケーションのメリット
それぞれ詳しく解説していきます。
Webアプリケーションは、インターネットを通してURLをクリックしてブラウザに繋げるだけで利用できます。つまり、アプリケーションをアプリケーションストアに通さなくても、アプリケーションをインターネット上に公開した時点で利用できるようになるのです。
そのため、Webアプリケーションを使いたいユーザーはアプリケーションをiPhoneやAndroidなどの端末にインストールする必要がありません。また、ユーザーがアプリケーションをインストールする分のストレージの容量を節約できるようになります。
ネイティブアプリケーションに比べて、Webアプリケーションは、比較的コストが低くなる傾向にあります。ネイティブアプリケーションはiPhoneやAndroidなどの端末にインストールするタイプのアプリケーションです。そして、それぞれの端末によって別々のアプリケーションを作らなくてはなりません。それぞれの端末に対応したアプリケーションを作るために、どうしても開発する時間やコストが多くかかってしまうのです。
一方でWebアプリケーションは、iPhoneやAndroidなどの端末にインストールしなくても、ブラウザ上で利用できる仕組みになっています。そのため、アプリケーションの開発にかかる時間やコストを最小限に抑えられるのです。また、インストールする手間以外に、アプリケーションの構造においても、コストがかかってしまう原因があります。ネイティブアプリケーションの構造は、非常に複雑になっています。一方でWebアプリケーションの構造はネイティブアプリケーションの構造に比べたら、そこまで複雑ではありません。アプリケーションは構造が複雑であればあるほど、アプリケーションの開発にかかるコストもかかります。そのため、より複雑なネイティブアプリケーションの方がコストがかかってしまうのです。また、アプリケーションストアの手数料なども関係しています。アプリケーションストアを通して、アプリケーションを販売しなければならないネイティブアプリケーションのほうが、アプリケーションストアを通さずにブラウザ上で利用できてしまうWebアプリケーションよりも、コストがかかってしまう傾向にあるのです。
Webアプリケーションは、サーバー上で一括で管理できます。インターネット上でアプリケーションを公開した後に行うアプリケーションの運用では、アプリケーションの修正やアップデートをする機会が多々あります。アプリケーションの修正やアップデートにおいて、ネイティブアプリの場合だと、アプリケーションストアを通して修正やアップデートを行わなければなりません。つまり、修正やアップデートを行うたびにアプリケーションストアからの申請や審査を受けなくてはならないのです。そうすると、一つの修正やアップデートだけに多くの時間がかかってしまう恐れがあります。一方で、Webアプリケーションはブラウザ上で直接公開しているため、アプリケーションストアの申請や審査が全くありません。アプリケーションの修正やアップデートがあったとしても、一度にスムーズに終わらせられるのです。
Webアプリケーションをインターネット上に公開する際は、審査が不要です。一方で、ネイティブアプリケーションは、審査を受ける必要があります。この違いには、アプリケーションストアが関わってきます。ネイティブアプリケーションは、アプリケーションストアを通してアプリケーションを公開しなければなりません。そのため、インターネット上に公開する際には審査が必要になるのです。しかし、Webアプリケーションは、アプリケーションストアを通さなくて良いため、そのまま自分の好きなタイミングで公開できます。審査を受ける手間が省けることや、アプリケーションの開発ができ次第、自分の好きなタイミングで公開できるのは大きなメリットといえるでしょう。
ここまで、Webアプリとクラウドアプリの違いや、それぞれの特徴について解説しました。
それでは、近年導入が進んでいるクラウドアプリには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここからは、クラウドアプリのメリットとして、次の4つのポイントについて解説します。
それぞれのメリットについて、くわしく解説します。
クラウドアプリの開発ではITインフラへの先行投資が不要で、開発期間も短期間で済むため、Webアプリの開発と比較しても開発コストを大幅に削減できます。
通常Webアプリを開発する際にはサーバーへの契約費が必要ですが、クラウドアプリの場合には企業がサーバーなどの機器を別途購入する必要なく、また運用に伴う管理費や電力費、空調費、保守費なども支払いが不要です。
またクラウドサービスを利用する際には柔軟な料金体系のなかから自社のニーズにあうプランを選択できるため、企業は利用するストレージや容量に対して費用を支払うだけでクラウドサービスを利用可能です。
少額の初期費用で導入手続きを進められる点において、クラウドアプリという選択肢はコストを安く抑えるポイントとして多くのメリットが得られる手段といえます。
クラウドアプリの開発では、自社で開発環境を整備する必要がありません。
Webアプリを開発する場合には、システム環境を自社のリソースを用いて構築・運用する必要があります。
そうした運用方法を「オンプレミス」と呼びますが、クラウドアプリの開発ではオンプレミスという方法を用いる必要がないため、アプリケーション開発に必要な機材を自社で準備する手間やコストを削減できます。
またオンプレミスでは自社で準備した機材を長期間使用する場合、劣化や故障といったトラブルから機材が廃盤になってしまうリスクがあります。
万が一廃盤機材が発生した場合には自社環境へ悪影響が懸念され、再度新たな機材をゼロから探す必要があるため、追加投資や工数増大に莫大なコストがかかる可能性があるのです。
その点において、クラウドを利用すれば自社で開発環境を準備する必要がなく、したがって機材が廃盤になるリスクも払拭できます。
クラウドアプリを開発する場合には、毎月使用した分のデータ量や容量にかかる費用のみを支払うだけで済むため、安定したアプリ運用が可能になります。
Webアプリの開発は設計から開発まで一連の作業をすべて自社で行う必要がありますが、クラウドアプリではすでに完成されたクラウドサービスを活用することでアプリ開発を進められるため、開発開始からアプリリリースまでの期間を大幅に短縮できます。
迅速な対応が要となるビジネスシーンにおいて、アプリ開発に必要な機関を大幅に短縮し短期間で新たなアプリを生み出せるシステムは、アプリの開発環境を迅速に整備できる点が大きなメリットとしてはたらきます。
クラウドアプリの開発では、リソース増減が発生した場合でも柔軟に対応できます。
Webアプリの場合、アプリを開発後いざリリースまで辿り着けても獲得できるユーザー数について明確に想定することは不可能です。
そのためアプリ開発を行う企業にとって、ユーザー数に応じてサーバー容量やリソースを確実に確保することが難しく、ユーザー数増加を見通した十分な準備が行えない点は大きな課題となります。
その点クラウドを利用すれば、ハードウェアに対する制約を受けることなくアプリの開発を進めることが可能であり、想定外のリソース増減が発生した場合にも柔軟に対応できます。
消費者ニーズが絶え間なく変化する現代において、柔軟な対応が可能である点は大きなメリットとして効果的にはたらきます。
ここまでクラウドアプリのメリットについて解説しました。
Webアプリの欠点を克服し進化させたクラウドアプリですが、両者には「ブラウザで操作できる」という共通点があります。
そのため、ブラウザを経由し開発を行うWebアプリの開発の流れは、クラウドアプリ開発の流れにも大きく関連しています。
そこでここからは、Webアプリの開発の流れを大まかに解説します。
アプリ開発を専門業者に外注する場合でも、開発の流れや仕組みを把握しておくことで業者とのやりとりやその後の進捗管理がスムーズに進みます。
Webアプリの開発の流れは、大まかに以下のような流れで進みます。
Webアプリ開発の流れについて、くわしく見ていきましょう。
アプリ開発を始める際には、アプリの構想を練る「企画・設計」の段階が非常に重要です。
アプリを開発する目的や、どのようなアプリをつくりたいかについて明確にすることで、その後の開発の流れが大まかに決定されます。
アプリの企画・設計は自社内で行うことも可能ですが、専門知識をもつプロからのアドバイスが必要な場合には、企画の段階から業者に相談し業者とともに開発を進めていく方法も有効です。
またアプリ設計の段階では、ターゲットとなるユーザーを想定しユーザーのニーズを想定することが大切です。
ユーザーが何を求めているか正確に理解することで、より高い品質の製品を生み出せるようになります。
ペルソナを設定する際には人口統計や行動パターンなどをもとに、潜在的ユーザーについても可能な限り調査を徹底するようにしましょう。
Webアプリを開発する際には、Webサイトの作成と同様にブラウザ上で動作する基本的な構成をイメージしましょう。
「どんな役割のページが必要か」「ページ同士をどのようなかたちで繋ぎ合わせるか」といったポイントを意識しながら、アプリ全体の構成を検討しましょう。
また、アプリの全体構造を大まかに把握できた段階で協力してくれる開発チームを探しましょう。
開発チームはアプリ開発の方法を構築したり、アプリの中核となる機能を選択したり、またアプリのコンセプトを設計したりしながら、本格的なアプリ開発に取りかかります。
そしてクラウドアプリの開発の場合には、開発チームが中心となってプロジェクトのマイルストーンを設定し、POC(概念検証)またはMVP(Minimum Viable Product)の開発を開始します。
アプリ開発では、長期的なプロジェクトに投資する以前に、アイデアの実現性をテストするための最適な手段を見つけることが重要です。
大まかな全体像が決まったら、アプリのデザインイメージやレイアウトなどを書き出し、デザインの設計図となる「ワイヤーフレーム」を作成します。
サイトマップを作成後、どのようなページが必要であるか明確に定まった段階でそれぞれのページデザインを考案しましょう。
ワイヤーフレームの設計に関して白紙の状態から業者に設計を依頼することも可能ですが、自社内である程度のラフを作成できたら、招集した開発チームのデザイナーにデザインを描き起こしてもらうことも可能です。
サイトマップとワイヤーフレームが完成し、Webアプリの全体像の構成が完了したら実際にプログラミングを行い、アプリを形作る工程に入ります。
Webアプリをプログラミングする場合でもWebサイトのプログラミングと仕組みは同様であるため「HTML」「CSS」「JavaScropt」などの言語を目に触れる部分に、そして「PHP」「Ruby」「Python」といった言語をWebアプリの動作や処理に関連する部分に使用します。
クラウドアプリの開発の場合では、Webアプリの開発と比較してプログラミング作業が大がかりかつ難解になります。
まずはMVP(Minimum Viable Product)を作成したうえで、技術的・ビジネス的なパフォーマンスを評価しながら作業を進めます。
MVP方式を採用することで、アプリケーションの長所や強み、欠点を把握でき、ユーザーからの提案を考慮しながらアプリケーションを改善することが可能です。
Webアプリを開発する際にも、Webサイト作成と同様にURLを取得する必要があります。
そして、URLを取得するためにはドメインとサーバーの設定が必要です。
ドメインとは「○○.jp」「○○.com」といったURL末尾につく英数字の○○にあたる部分です。
一般的には、サービス名やアプリ名がドメインに採用されます。
またドメインの取得には1年間で約1,000~2,000円の費用がかかります。
一方サーバーの取得には1カ月あたり1,000~2万円程度がかかりますが、アプリの内容が複雑だったりユーザー数が多かったりするほどサーバー費用は高額にのぼり、状況によってサーバー取得費用は変動します。
ドメイン取得費用とサーバー費用は基本的に開発費用に含まれ算出されますが、予算計画の際に見積りを申請した時点でこれら費用についてもしっかり確認しておく必要があります。


アプリが完成したら、納品作業を行ったうえでアプリをリリースします。
リリース直前には徹底的なテスト作業が必要です。
テスト段階では「アプリが正常に起動するか」「ユーザーにとって快適な操作性になっているか」などのポイントを中心に隅々までアプリ動作のチェックを行います。
社内環境でテスト作業を行うキャパシティがない場合には、海外地域に業務を委託する「オフショア」を活用することで、リソース戦略や立ち上げ準備といった作業に社内の人員を多く動員することが可能です。
ここまで、Webアプリ開発の大まかな流れについて解説しました。
Webアプリの開発では設備費や人件費など、多くのコストが発生します。
それでは、Webアプリ開発の費用を安く抑えるには、どのようなポイントをおさえる必要があるのでしょうか。
ここからは、Webアプリ開発の費用を安く抑えるコツとして、3つのポイントについて解説します。
アプリに多くの機能を搭載するほど、開発費用は高額にのぼります。
そのためアプリを設計する際には必要な機能を明確にし、不要な機能を削除することでコスト削減が期待できます。
機能の取捨選択をする際には自社内でアイデアを募るだけでなく、業者からのアドバイスを参考にしたり、実際にアプリをリリース後にユーザーからの声を参考にしたりすることで効果的なアプリ設計が可能になるでしょう。
アプリ開発にかかる費用を自社でまかなえない場合には、補助金の利用もおすすめです。
アプリ開発に利用可能な補助金には、具体的に以下のような制度が挙げられます。
最大補助額がもっとも多いのが「事業再構築補助金」で、最大1億5,000万円まで補助を受けられます。
事業再構築補助金は基本的にインターネットを通じて申請可能で、補助率や補助金額は従業員数に応じて変動します。
また中小企業でアプリ開発を行う場合には「小規模事業者持続化補助金」がおすすめです。
インターネットもしくは郵送で申請可能で、商工会または商工会議所から直接支援を受けられます。
そのほか補助金ごとに補助対象や補助率、最大補助額は異なるため、自社の状況にあわせて最適な制度の利用を検討しましょう。
アプリ開発を業者に依頼する際には、業者ごとに開発費用が異なります。
そのため、事前に見積もりを申請する際には必ず複数社に対し相見積もりを申請し、複数社の料金プランや費用項目、金額内訳を比較・検討することで自社のニーズにあう業者を選びましょう。
ここまで、Webアプリの開発費用を安く抑えるためのポイントについて解説しました。
開発費用を大きく左右する要因として、業者選びは非常に重要です。
それでは、実際に業者を選ぶ際にはどのようなポイントを意識すべきなのでしょうか。
ここからは、Webアプリ開発の業者を選ぶ際に重要視する3つのポイントについて、それぞれ解説します。
業者選びで着目すべきポイントとして、どれほど数多くの実績を残している業者であるか、というポイントが重要です。
多くの開発実績をもつ業者に依頼すれば、さまざまなニーズに柔軟に対応できる経験と知識で、自社の希望に沿ってアプリ開発を進めてくれるでしょう。
また業者のホームページで実際の事例を閲覧できる場合には、どのような技術をもっているか、どのような強みがあるかについて正確に把握できます。
業者ごとにアプリ開発にかかるコストは異なるため、業者選びの際に開発コストを確認するプロセスは非常に重要です。
単純に費用総額を相場と比較するだけでなく、どの工程にどれだけの費用が必要であるかといった細かな金額内訳まで確認し、適正な価格設定であるかを検討しましょう。
業者選びをするうえでユーザーからの評価や評判は重要な判断材料として役立ちます。
例えば「納期が遅い」「連絡がつきにくい、レスポンスが遅い」といったネガティブなレビューが多い業者は避けたほうがよいといえます。
また顧客の声を確認する際には、悪い点だけでなく良い点にも着目し、その業者を選ぶことでどのようなメリットが得られるかについてしっかり確認しましょう。
Webアプリとクラウドアプリには仕組みや構造に違いが見られ、Webアプリの利便性をさらに高め進化させたものがクラウドアプリであるといえます。
クラウドアプリはブラウザ上での操作はもちろん、専用アプリを端末にインストールしておけばオフライン環境でも一部の機能を使用できます。
「Webアプリとクラウドアプリ、どちらがよいか迷っている」という事業者様は、ぜひEMEAO!までお問い合わせください。
簡単なヒアリングを行ったうえで、事業者様のご希望に沿った優良なアプリ開発会社を最短即日で紹介させていただきます。
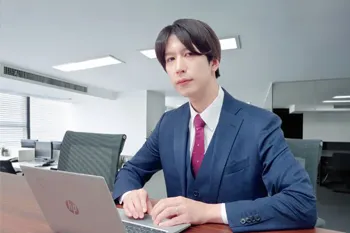
プロフィール
異業種で営業経験を積んだのち、Web業界に可能性を感じて株式会社ecloreに中途入社。
現在は、お客さま対応を担う。年間実績として、120社を超えるクライアントのSEOコンサルを担当。
より高いSEO成果をご提供するために最新のSEO情報とクライアントからの要望を元に日々サービスの品質改善に取り組んでいる。
【対応実績事例】
https://rank-quest.jp/column/episode/life-adj/資格
∟SEO協会認定試験とは:時代によって変化してきたSEO技術を体系的に理解していることを示す資格検定試験です。
Google アナリティクス認定資格∟Google アナリティクス認定資格とは:SEO対策には欠かせないデータ解析ツール「Googleアナリティクス」の習熟度をGoogleが公式に認定する資格です。
公式アカウント
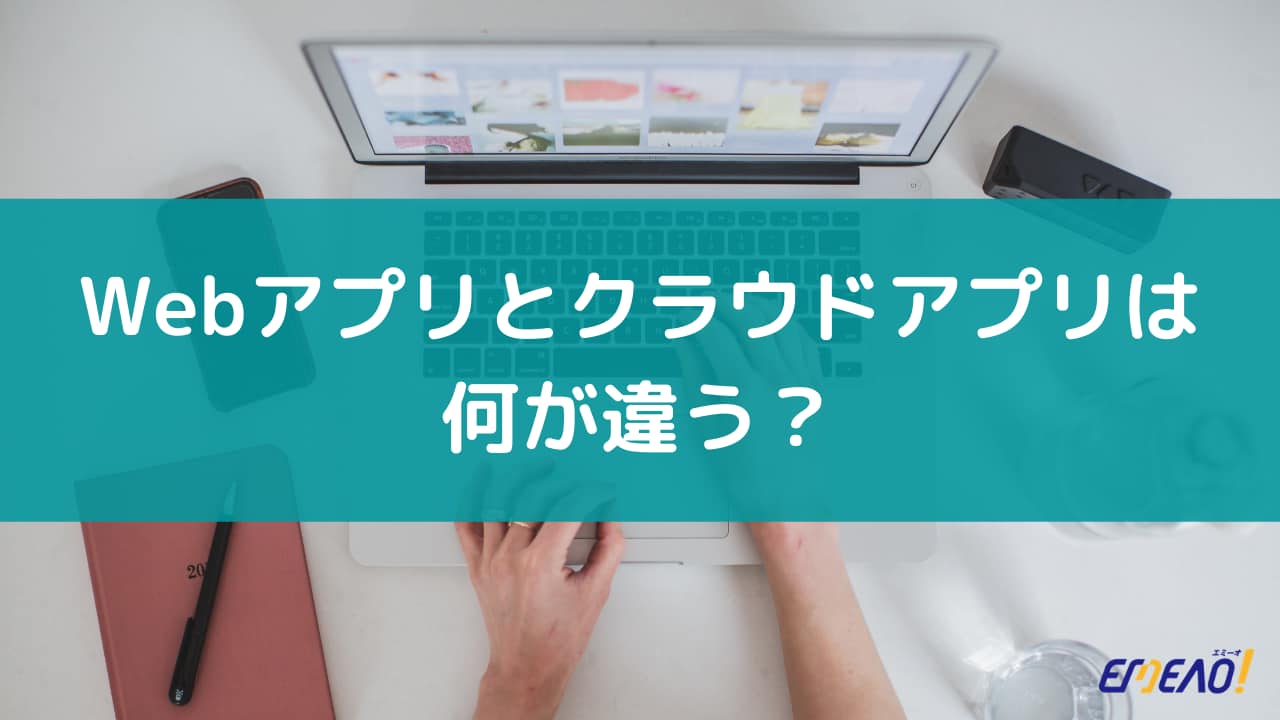

 発注先選びのツボ
発注先選びのツボ 
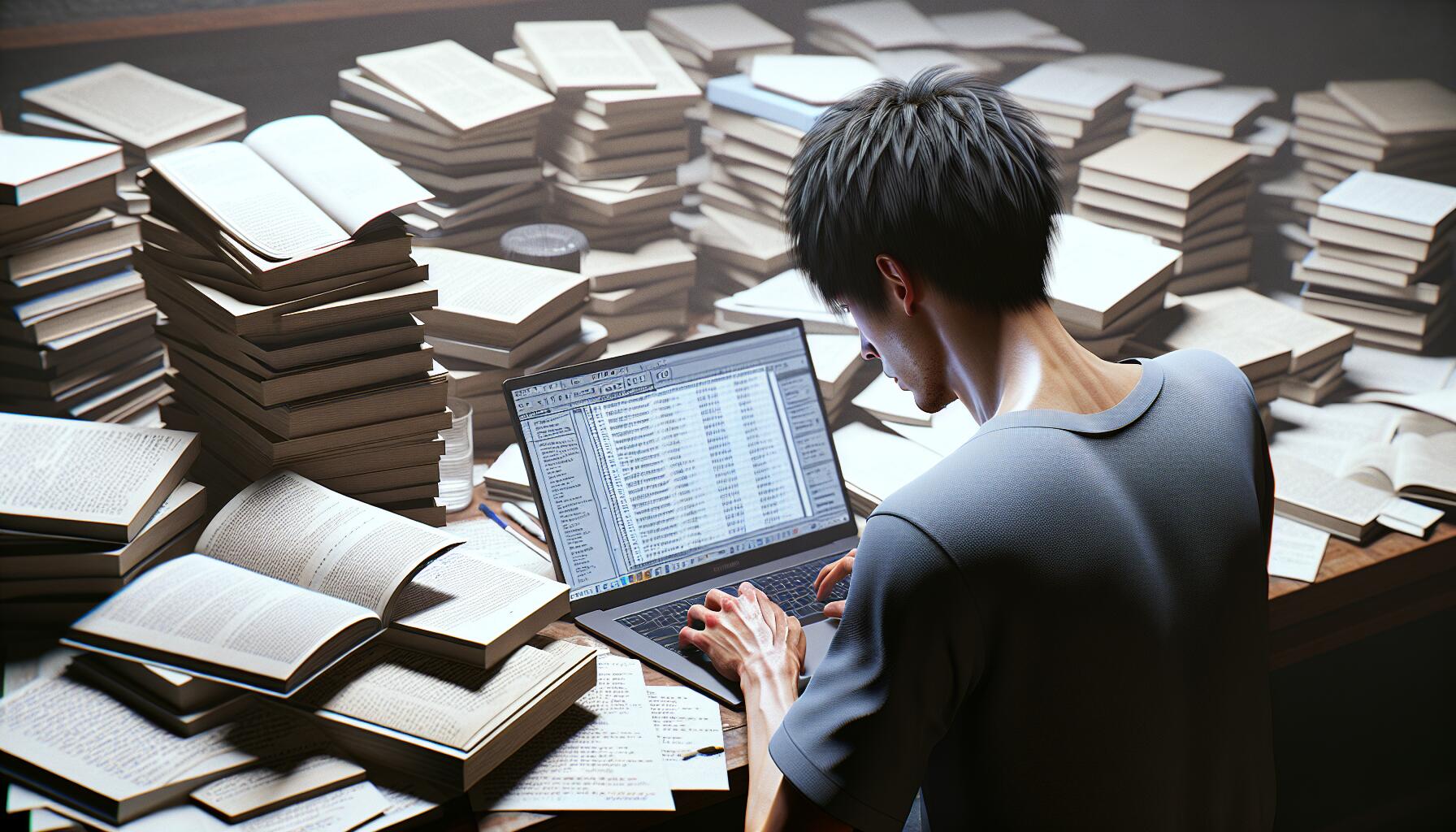
 発注先選びのツボ
発注先選びのツボ 

 発注先選びのツボ
発注先選びのツボ 

 発注先選びのツボ
発注先選びのツボ 

 発注先選びのツボ
発注先選びのツボ 

いろいろな業種の「発注のお悩み」を解決するウェブマガジンです
このサイトは、専門業者紹介サービス、エミーオ!が運営しています。エミーオ!は、発注したい仕事の詳細をお伺いし、それに応えられる業者を紹介する完全人力サービス。
自動化された見積もり比較サイトとの違いは、お客様の問題解決に注力していること。専門性の高いスタッフが案件を理解した上で業者を選定しています。
このウェブマガジンは、エミーオ!を通して得た、さまざまな業種のお悩みや旬の話題をお届けしています。

業者選びのコツがわかるから失敗を防げる

関係あるビジネスの
トレンドがわかる

今さら聞けない業界知識がよくわかる
